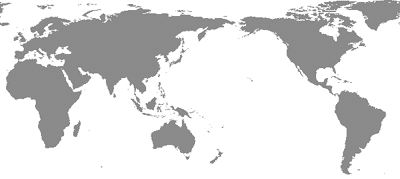今週と来週の2回の講義では、スーザン・ジョージ(Susan George)の『なぜ世界の半分が飢えるのか──食糧危機の構造』(Susan George, How the other half dies: the real reasons for world hunger, Penguin Books, first published in 1976/小南 祐一郎・谷口 真里子訳、朝日選書257、朝日新聞社、1984年)を取り上げます。前回は言いませんでしたが、第5章の「緑の革命」も追加して取り上げたいと思います。
先週の授業の補足──ポール・ハリソン『破滅か第三革命か』訳文修正案の修正
それでちょこっと遡って、訂正があります。
前に配ったポール・ハリソンの『破滅か第三革命か』の訳文修正案のプリントの3ページを開けてください。そこに『破滅か第三革命か』の90ページ、12-13行目の「多数の動植物は競争相手がなく、多様な生態学的地位に放射状に配置されている」(原文はp.74の「Many families of animals, finding themselves without competitors, have radiated into a multiplicity of niches.」)という文章の修正案として、「…様々なニッチを見つけ繁殖している。…」と書きました。しかし、ちょっとこれでは充分ではないということがわかったので、さらに修正をします。この部分を「進化の枝分かれをして、様々なニッチに繁殖している…」と修正してください。「繁殖」という言葉がいいかどうかはもう少し検討する必要があるかもしれません。
生態学ってみんな授業でやっているんだよね。生態学は非常に重要ですよ。英語では「ecology」って言うんだよね。生態学では「ニッチ(niche)」という言葉が出てきますね。ここでは「niches」と複数形で使われていますね。それで「進化の枝分かれ」の方は「radiate」と言うようです。「進化の枝分かれ」なんて言葉ではなくて、たぶん学術用語があると思いますが、探してみてください。そういう修正案でした。
大型の英和辞書を引いてみたところ、「radiate」はこの場合「放散」と訳すのが一番しっくりきそうです。「放散」を『岩波生物学辞典 第4版』(八杉 龍一ほか編、岩波書店、1996年)で引いてみると、「適応放散」という項を参照となっていました。以下に一部分を抜き出しておきます。
「適応放散」英 adaptive radiation 仏 radiation adaptative同一類の生物が種々の異なった環境に最も適した生理的ならびに形態的分化を起して多様の異なった系統に分岐し、時間の経過とともに分岐の程度が強まること。
スーザン・ジョージが探求するもの
さて、今日の本題スーザン・ジョージに戻りましょう。
柳田國男「火の昔」(今回使用したのは『柳田國男全集 第14巻』所収、筑摩書房、1998年)をみんなに読んでもらって、それからマルクスの『ライン新聞』(第298号、1842年10月25日)に書いた論説「材木窃盗取締法にかんする討論」(『マルクス=エンゲルス全集1』所収、大月書店、1959年)を読んでもらったよね。このふたつは同じテーマを扱っていませんか。同じテーマを扱っていると僕は思っておりますが、みなさんはどう思っているでしょうか。
中尾:野村くんはどう思っている?
野村:けっこう同じだと思います。
中尾:「けっこう同じ」だよね。だけど探求の方向が全然──「全然」という言い方は少し問題があるかもしれませんが──違いますね。
柳田國男は生活の技術とか、「文化」──柳田國男は「文化」という言葉を使いたくないと言っていましたけど──自分たちの先祖、あるいは自分たちが一生懸命つくってきた生活の方法、技術というところに焦点をあてる。またはそれをますます深く追究をしたということになっています。片やマルクスは何をしたんでしょうか。マルクスの追究はどこへ向かっていたんでしょうか。
竹内:議会の法律をつくることです。
中尾:そう、法律をつくる世界にマルクスの追究は向かっていたんだね。しかし、その追究はどういうものかというと、「おかしい」っていう話だね。
「これはおかしい。理不尽である」ということでした。これをふたつの方向性と言ってしまうのは、僕は嫌なんですけれども、とりあえずそれぞれに違う方向性であるというふうに考えてみましょう。とりあえずね。
しかしスタートはどこにあるかというと、結局のところは薪を拾いに山に入る人たち、その薪を使って火を起こす人たち、そういう人たちがいるんだよね。そこが出発点になるというふうに考えたいと思います。その薪を使って火を起こす人たちはポール・ハリソンの本のなかにもでてきましたね。
言ってみれば、人間が環境のなかでどうやって生きるかということに「火」は欠かせない。それは人間の原罪かもしれませんが、火を使わない人間はいない。仮に「自然」という言葉を使えば、「自然」と人間の接点で起こっていることのひとつは「火」です。もちろん、「水」とか「土」とか、いろんなものが次から次へと想像されるけれども、とりあえずここでは、「火」の問題をめぐってマルクスと柳田國男が探求の方向性を明かにしたということがわかった。
ここからまた「発展」──と言うかどうかはわかりませんが──して、スーザン・ジョージをみなさんに読んでもらいました。食べ物・食糧ということが、スーザン・ジョージの探求の中心にありますが、その食べ物に関わるのは当然のことながら柳田國男的な方向性もあれば、マルクス的な方向性もあるよね。それから、もしみなさんが読んだポール・ハリソンをそういうことで言えば、どういう方向性の考え方であったかというふうに評価することができるか考えてみてください。
スーザン・ジョージはどんな人か?
さあ、そのスーザン・ジョージですが、いつごろ生まれた人か知っているよね。書いてなかった? 不思議なことにどうも女の人の生年を書かないという習慣があるようですが、スーザン・ジョージという人は1934年生まれだったと記憶しています。
さっき配った資料の彼女の著作が並べてあるところを見てください。彼女が書いたものには、『ルガノ秘密報告──グローバル市場経済生き残り戦略』(毛利 良一、幾島 幸子訳、朝日新聞社、2000年/Lugano report: on preserving capitalism in the twenty-first century、Pluto Press、1999)というのがあります。それからFaith and Credit: the World Bank’s secular empire(with Fabrizio Sabelli、Penguin、1994/ファブリッチオ・サベッリ共著、毛利 良一訳『世界銀行は地球を救えるか──開発帝国五〇年の功罪』、朝日新聞社、朝日選書567、1996年)というのがありますね。それからThe debt boomerang: how Third World debt harms us all(Pluto Press、1992)というのがありますが、日本語のものは朝日新聞社から出ています(佐々木 健、毛利 良一訳『債権ブーメラン──第三世界債務は地球を脅かす』、朝日選書539、1995年)。
中尾:みんな「debt」ってわかるよね。
竹内:債務ですか?
中尾:そう。「負債」、「債務」、「借金」、「借り」ということだね。
要するに、この『債権ブーメラン』という本は、IMFを通じて──その他いろいろ銀行がありますが──日本のような国がいわゆる発展途上国にお金を貸すけど、借りた国はそれが返せなくなるという状況になって、「ブーメラン」と表現されているとおり戻ってくる。そういうことが世界で起こっているということを書いたものです。
それからIll fares the land: essays on food, hunger, and power(Penguin、1990)というのがあります。これは日本語訳はないようです。それからA fate worse than debt(Penguin、1987)というのがあります。これは日本語の方は『債務危機の真実──なぜ第三世界は貧しいのか』(向 壽一訳、朝日新聞社、朝日選書380、1989年)というタイトルで出ています。それから今日これから取り上げるHow the other half dies: the real reasons for world hunger(Penguin、1976)の日本語訳は『なぜ世界の半分が飢えるのか──食糧危機の構造』(小南 祐一郎、谷口 真理子訳、朝日新聞社、朝日選書257、1984年)というタイトルになっていますね。(「dies」という言葉が)「死ぬ」とは訳されていません。「飢えるのか」と訳されています。原題を直訳すれば、「なぜ半分が死ぬのか」となっているね。その他まだまだフランス語のものなんかがありますね。
それから最近、2冊くらい続けざまにでましたね。『WTO徹底批判!』(杉村 昌昭訳、作品社、2002年/Remettre l’OMC à sa place, Attac Les Petits Libres No.34, Mille-et-une-nuits, 2001)と『徹底討論 グローバリゼーション賛成/反対』(マーティン・ウルフ共著、杉村 昌昭訳、作品社、2002年/Pour & Contre. La Mondialisation Libérale, with Martin Wolf, Grasset, 2002)というタイトルです。いずれも世界銀行とかグローバリゼーションをめぐって、スーザン・ジョージが闘っている本です。スーザン・ジョージがどういう人であるかということがだいたいわかったかな。
今日の本題──スーザン・ジョージ『なぜ世界の半分が飢えるのか』
さて、『なぜ世界の半分が飢えるのか』に入りたいと思います。みんな読んできてくれたかな。半分でも読んできた人、ちょっと手を挙げてくれる。(ぱらぱらと挙がった手を見て)そうか…。先週とほとんど変わらない状況であるということがわかりました。
みなさんに読んできてもらうことになっていたのは、第3章の「第三世界の特権層」ですね。それから第4章「技術──だれのためのものか」というところでしたね。それから今日、第5章の「緑の革命」、第7章の「アグリビジネス──この素敵な商売」、それから第10章「“彼ら”に何ができるか」と第11章「あなたに何ができるか」というところを追加しました。
では、第3章の「第三世界の特権層」というところを見てください。読んだ人は「何これ?!」と、ちょっと驚いたと思います。
世界大戦というのがふたつあったことになっています。この前のは第二次世界大戦でした。この次に起こるのは第三次世界大戦ということになりますね(笑い)。できるだけ第三次世界大戦は起こってほしくないと思います。第二次世界大戦というのは、本当に全世界規模で戦争になったんですね。その戦争に勝った国家はどこであったか。連合国側が勝ったということになっています。ところが、その連合国というのには、その後世界を二分する大きなふたつの勢力が含まれていましたね。ひとつはアメリカで、もうひとつはソ連という国でした。あるいは、人によってはそこにもうひとつ中国をくわえたほうがいいんじゃないかという考えかたもなくはない。
しかし、みなさんが知っているとおり、第二次世界大戦で本当に勝った(傷つかなかった)、ますます力をつけたのはアメリカでした。もちろんアメリカの兵隊さんは死にました。しかし、第二次世界大戦後の世界をつくる主動力にアメリカがなるというかたちで、戦争は終わりました。
主として、この『なぜ世界の半分が飢えるのか』の第3章に書いてあるのは、その第二次世界大戦後のアメリカの世界への関わりかたが書かれています。この授業では、いささか偏向してさかんにアメリカ攻撃をしているようです。1949年のトルーマン大統領の就任演説を意味ありげに取り上げたりして、結局のところ現在の世界──産業社会──がアメリカをモデルにしたり、あるいはアメリカの推進力におされて成立をしたり、あるいはアメリカに従属をしてこの産業社会が形成されてきた。もう少し言うと、つまり「開発」という言葉はそのために使われてきた、というような言いかたをしてきました。
スーザン・ジョージはこの第3章でそのことをもっと露骨に言っています。露骨というよりは具体的という言葉のほうが適切ですが、具体的には、生きている人間が関わらないと事は起こりませんね。その生きている人間は、(この章のなかに)名前まで挙がっていたりします。どういう人たちが、その「開発」政策を進めてきたかということが書かれています。もちろんここに書かれていることが全部ではありません。スーザン・ジョージが全部を事細かに書いたわけではないですが、こういうふうにいわゆる「政治的な力」あるいはその背後にある「金銭的な力」──「金銭的な力」という言葉があまりに下品であれば、「資本主義」とかいう言葉に置き換えてもいいわけですが(笑い)──とかそういうものがあった。しかも──みなさんはこの章を読んで読みとれたと思うんですが──そういう力と同時に世界が共産主義にならないようにという考えも同時に存在したというふうに書かれていたと思います。
「第三世界」とはどこか──「世界」=西側諸国!?
さあ、ちょっと具体的に見てみましょう。「第三世界」という言葉が出てくるよね。
中尾:第三世界ってなんですか? 誰か答えてくれる人いない?
齋藤(卒業生):東と西とはまた別の勢力
中尾:さすがにおじさんは…(笑い)。
齋藤:(笑い)
中尾:「東と西」と言いましたが、「東」ってなに?
齋藤:ソビエトとか東ヨーロッパあたりだと思います。
中尾:不思議なんだよね。(世界地図を指し示しながら)地図でみるとソビエトってこの辺にあるでしょう。東ヨーロッパってこの辺です。ソビエトはこんなにでっかいんだね。いまはロシアになって、このなかはいくつかの共和国にわかれていますが、その当時はソビエト連邦という、地理的にも大きいけれども、その他の意味でも非常に大きなひとつの勢力だったんだね。
ここに中華人民共和国というのがあります。これが東なんだよね。この地図(日本列島がほぼ中心にあり、南北アメリカ大陸が向かって右端、ユーラシア大陸、アフリカ大陸が左側に描かれた世界地図)上の東はどっちですか。(地図の右側を指しながら)東はこっちだよね。アメリカが東じゃないかと思うかもしれないけど(笑い)、それはこういう地図を見るからそういうふうになるんだよね。でもこの地図を太平洋の真ん中で切って、アメリカ大陸が左にある世界地図をつくると、ソ連や中国が東なんだよね。日本というのは非常に変な位置にある。極東って呼ばれる位置だね。でもこの地図では日本は極東じゃないね。アメリカの方が東だね。つまり日本を極東と言うときに使う地図は、アメリカが向かって左側にある地図だね。簡単なことだね。
それで、そうするとヨーロッパの真ん中あたりからこっち(左側)──アメリカ、カナダが「西」なんですよ。わかった? これが「第一世界」。でもふつう「第一世界」とは言わない。じゃあ、何て言うのか。「The world」──「世界」っていうんだよ。これが「世界」(笑い)。
それで東ヨーロッパから中国あたりまでの部分──極東はちょっと別扱いして、抜かすんですが──を「東」と言うんです。これが「第二世界」です。しかしながら、この「第二世界」のことを「The second world」とは言いません。でもさっきの「The world」というのは冗談じゃなくて、アメリカと西ヨーロッパについては「世界」って本当に彼らは呼ぶんだよ(笑い)。
オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国あたりはどうなっちゃうかというおもしろい問題がありますが、それはちょっとおいておいて、それ以外のところを「第三世界」という言葉を使って呼びます。いまでも「第三世界」という言葉を使っているんですよ。そんな言葉を使っていいかどうか、しばらく議論になると思うけれども、「第三世界」というのはいま言ったようなところを指しています。
思い返していただきたいのは、1945年に日本が(戦争に)負けた時点、それからその後しばらく──日本がいまのようになるのには相当時間がかかりましたけど──例えば1ドルが360円と決まっていた時代(つまり1950年代)には、たぶんアメリカの目(別の言いかたをすれば第一世界的な目)から見れば、極東の日本は第三世界だったんですよ。アメリカにしてみれば、日本は第三世界で経済開発に成功したものすごい模範的な例だと思います。ただみなさんがこのスーザン・ジョージを読んで少し考えたらわかったと思いますが、どうやら他の地域と日本が持っていた条件は全然違います。そういうようなことを少しずつ読みとっていただきたいと思います。
スーザン・ジョージが描いた第三世界の例──インドネシア
さて、ひとつの典型的な例として、インドネシアの事情をスーザン・ジョージは少し描いています。インドネシアというのは、ものすごくややこしいですね。それでもなにか言おうとすれば、ややこしいことを抜かして、おおざっぱな言いかたをするしかない…。
さあ、インドネシアというのはどこにある? インドっていうのはどこにある? (地図を指し示しながら)インドはここだよね。インドネシアはどこだ? インドネシア知らない人は? 知っている人は? (たくさん挙がった手を見て)おお、よかった。知っている人がいた。(もういちど地図を指して)インドネシアはここだよね。
よくよく見ると、この地図は1972年くらいのもので、ちょっと古いんですね。古いんですが、この地図の黄色くなっている部分の東半分が東チモールですが、この地図にはそういう区分けはなくて、すべてインドネシアになっています。それから(地図を指しながら)これがみなさんご存知のパプア・ニュー・ギニアです。これはニュー・ギニア島というんですが、これを半分に切って西側が西イリアンと言うんだね。この西イリアンまでがインドネシアの領土になっています。それから、(地図の島を指して)この大きな島、ここにはマラッカ海峡というのがあるんですが、スマトラ島、ジャワ島、それからボルネオというのをご存知だと思いますが、ボルネオの北の方はマレーシアです。こっち(南)の方がマレーシアです。このへんに山ほど島がありますが、そこを全部まとめてインドネシアという国をつくったんですね。
誰がつくったか? 誰がつくったかというのはちょっと変な言い方だけど、インドネシアをつくった政治的指導者はスカルノ(Sukarno, 1901-1970)という人です。こういうインドネシアの国家がここにつくられるまでは、ここはポルトガルとかオランダとかドイツとかという国が植民地にしていたんだよね。オランダの勢力が大変に強かった。みなさんご存知のように、マレー半島はイギリスが植民地にしていたんだよね。フィリピンは最初はスペインでしたが、その後アメリカが植民地にしていましたね。それから、この地図では仏領インドシナと書かれている国がありますが、いまはベトナムとカンボジアとラオスになっています。それからオーストラリアもイギリスの植民地でしたね。このような植民地世界が第三世界と呼ばれるもののひとつの代表例ですね。そして、とりわけそのなかのインドネシアという国に焦点を当ててみましょう、とスーザン・ジョージは言っているわけですね。
先ほど少しでてきましたが、スカルノという人がいます。スカルノの奥さんを見たことがある人いる? デヴィ・スカルノっていう人がいるよね。デヴィ夫人と呼ばれているね。彼女は何番目の夫人でしたっけ? たしか銀座あたりでスカルノさんと出会っただったよね。デヴィさんは日本で生まれて日本で育った人なんですが、スカルノさんが日本に来たときに、「この人(デヴィさん)はいい女性だ。私の奥さんになってほしい」と言われて奥さんになったんだよね。
スカルノさんを悪く言うためにこういうことを言っているんじゃなくて、スカルノさんがさっき説明したような国家をつくるのには大変な時間がかかりました。簡単にはできなかったんです。戦争が終わったのは1945年ですが、インドネシアが国家として独立をしたのはいつのことでしょう。考えたって知らないものはでてこないよね。こういうのは調べるといいね。すぐには(スカルノのつくろうとした国家は)できなかったということを覚えておいてほしい。
さて『なぜ世界の半分が飢えるのか』の90ページを見てください。ここに書かれている話は、すでに1950年代に入ったころのことです。これはスカルノの建国がひととおり終わったころです。例えば、さっきの地図で説明した「西側」にも「東側」にもどっちに親しくする態度はとりませんという「非同盟主義」を彼は唱えるんだね。スカルノさんのほかに非同盟主義を唱えた人たちは、例えばインドのネル(Pandit Jawaharlal Nehru, 1889-1964)とか、後に暗殺されそうになっちゃうエジプトのナセル(Gamal Abdal Nasser, 1918-1970)という人がいます。こういう非同盟主義の人たちが第三世界のなかにはいたわけですね。彼らはアメリカ寄りの立場をとらない。ソ連寄りの立場をとるわけでもない。そういう主義の人たちです。
インドネシアに戻りましょう。そういう非同盟主義のインドネシアに1950年代に起こったことはなにかと言うと、スカルノさんがさらに国家運営を続けていくという政治的足場固めをするんですね。それが1955年の総選挙、それから1957年の地方選挙であった。それで、スカルノの「政府は外国資産の国有化を始めた」(『なぜ世界の半分が飢えるのか』p.90)と書いてあります。これはやばいよね。「外国資産の国有化」ってどういうことだろう? つまり、いままで外国の人が所有権を持っていたようなものがあるとしても、領土のなかにあるものはすべて国家のものです、というふうに言っちゃうということです。これは大変です。
それで、そんなことにならないようにということで、親西側政党──これは小さなものがふたつしかなかったと書かれていますね──に、勢力を結集した旧貴族階級と地主たちはCIAから短期間の──長期間ではなく──支援を得て反乱を企てたが失敗に終わりました、と書かれています(同 p.90)。それでスカルノは、この反乱を企てた指導者たちを追放して、彼らの政党は非合法であると言って解散させてしまった。これは(西側──アメリカは)ますます困った。それで、これはますます本腰を入れて、インドネシアのなかに西側の利害を支えるような組織をつくっていかなければならない、というふうに(西側──アメリカは)感じるわけですね。
その先の文章をちょっと見てください。「明らかに絶望的なこの状況をただそうと決意した」(同 p.90)というところの「絶望的」というのはいったい誰にとって絶望的なのかというのを注意していただきたいんです(笑い)。つまり資産を没収されちゃうという立場の人だよね。つまり、インドネシアのなかではもう儲けることができないということが絶望的状況ということですね。
「近代国家は近代的エリートなしにはあり得ない。われわれが大学教育に力を入れてきたのはそのためである」(同 p.90)とあります。なるほど、大学の使命(注1)ってこういうことか、とようやくわかるわけです(笑い)。つまりエリート、アメリカとか西ヨーロッパ勢力の言うことをきく人たちをどうやって組織するかという課題があった。
「フォード財団(Ford Foundation)」というのが次の文章にでてきますが、「フォード」って知っているかい? 「フォード財団」知らない人? 自動車の「フォード」は知っている人? 自動車のフォードだと思ったらよろしい(笑い)。「フォード財団」っておもしろいですよ。その次をもうちょっと読んでみよう。
「フォード財団は、開発の“政治的障害”となるようなインドネシアの社会のさまざまな側面を調べるため、アメリカの有名大学、とくにマサチューセッツ工科大、コーネル大、バークレー(カリフォルニア大)、ハーバード大などを利用した」(同 p.90)
マサチューセッツ工科大学っていうのは、「MIT」って言うの知ってる? 「Massachusetts Institute of Technology」のことです。ここは賢い人がいっぱいいるんだよね。それからコーネル大学(Cornelle University)も東海岸にある大学ですが、京都精華大学が提携を結んでいるコーネル・カレッジではありません。コーネル・カレッジはアイオワ州の小さな、小さな大学です。それからバークレーというのは、カリフォルニア大学のバークレー校の意味です。ここも賢い人がいっぱいいます。ハーバード大学も東海岸の大学ですね。マサチューセッツ州にありますね。ここに書いてある「利用した」ってどういう意味だろう。つまり、これらの大学がいろいろ調査研究をしたという意味ですね。
それと並行して、アメリカ国内では貴族出身のインドネシア人をふんだんに金を使って訓練した(同 p.90)
精華大学にはこういうことはできない(笑い)。それでこのインドネシアの人たちは後に、「“バークレー・ボーイズ”として知られるようになった連中」(同 p.91)として書かれています。インドネシアの政府のなかにバークレー校出身という人が山ほどいるんですね。それを指して「バークレー・ボーイズ」と言う。
その数行後に「フォード財団は、知識人の交流を、スカルノ失脚の際にインドネシアの指導者となる連中の訓練だと考えていた」という財団当局者の話の引用があって、さらに「“スカルノの急死に伴う混乱防止”のための“偶発事件計画”を準備したりした」(同 p.91)と書かれています。どうやって急死するのかということは書かれていませんが(笑い)、そういうシナリオがあったようです。変なこと言いますね。「偶発事件」は計画されるわけはないんですが、計画される偶発事件というのを考えた。それで1965年までに4000人以上がカリキュラムを終えて卒業したわけですね。その人たちがインドネシアに帰ったら、やっぱりこの4000人という数はすごい勢力ですよ。
それで「ジャーナリストの間では、“忍びよるクーデター”を口にする者もでるようになった」(同 p.91)とありますが、この「ジャーナリスト」というのは、インドネシアのことをいろいろ取材をしたりするジャーナリストという意味だね。つまり、ジャーナリストたちの間で、スカルノ政権をこのアメリカで訓練を受けてきた人たちがひっくり返すんじゃないだろうかと考える人がでてきはじめたということだね。さらに続きを読んでみましょう。
「あるアメリカ人の教授は、この軍人・経済学者の連携をさして、新型政府──軍と私企業の政府と呼んだりした。…」──しかし、まだ共産党は勢力を持っていたわけです。それで共産党は議会での勢力を維持しようと考えて──「…軍との連合政権に加わった。そして、やがては共産党が勝利する日が来るであろうと考えていた」(同 p.91)と書いてあります。スカルノ自身は共産党ではありません。でもそういうことがあったんですね。
しかし、土地改革が後退をする。土地改革というのは、一般的に言うと、大きな土地所有者、つまり貴族階級がいて多くの小作民を抱えているような状況をやめて、小作だった人たちが自分の土地を持てるようにすることです。それが停滞をしちゃうと農民に不満が高まる。その高まった不満を軍隊が鎮圧するということが繰り返されるようになった。そうすると軍隊のなかに、結局は平等主義ではなくて、大地主の利害のために働くような力があるということがわかって、共産党はこれでは民兵の必要性──民兵必要性というのは、国の軍事力ではなくて、農民自らが軍事力を持つようにならなければならないということですね──を考えたんだけど、もうそのときは遅かったよという状況が簡単に書かれています(同 pp.91-92)。
ではちょっと92ページを見てください。「軍部は国家のなかの国家となってしまった」とありますが、この軍部にアメリカで教育を受けた人たちがたくさんいたわけですね。気がついてみれば、「銃を持っていたのは、スカルノやインドネシア共産党でなく、軍部だったのである」(同 p.92)と言っています。それはそうだよね。軍部が持ってたんだね。
ここからが悲劇だけど、「いよいよ学生たちが舞台に上がる時がきた」とある。その学生たちというのは誰か。これは「“バークレー・ボーイズ”はじめ、ケンタッキー大学の“制度改革”計画、CIAの主宰する指導力養成留学生計画などによって訓練されていた連中である」と書いてあります。「連中である」という訳語はいかがなものがと思いますが(笑い)、しかし「連中」なんですね。「それに加えて、インドネシアの全有名大学の学生は、軍隊によって準軍事訓練を受けていた。この訓練ではバークレーから休暇でやってきたアメリカ軍の大佐が指導に当たっていた」(同 p.92)とあります。こういうようにして、アメリカの影響力がスカルノの国家構築計画を挫折させることになります。
その次の一行に注目してください。「彼らは“農村地帯における過激派の回教青年グループ”と手を結んだ」(同 p.92)とあるね。ええっ、いまどうなってんの? と思うでしょう。わかった? いろいろわかってきたよね。第一世界があって、第二世界があって、第三世界は地域的には非常に大きいわけです。インドネシアに焦点を当ててみると、ここ(インドネシア)でアメリカは回教の過激派グループと手を結んだ。みなさん、ちょっと前に聞いたことがあるよね。アメリカはこの辺(地図のアフガニスタン付近を指しながら)で回教の過激派グループと手を結んだ。これはいろんな段階がありますが、みなさんが一番よく知っているのは、結局のところアフガニスタンで回教の過激派グループと手を結んで、ソ連と闘った。ソ連が出ていったあと、回教の過激派グループはアメリカと敵対関係になって、9月11日が起こった。インドネシアでもそれと同じようなことをやった。だいたいどこでも同じようなことをやるんだね。
さらに続きを読んでみると、「共産党の中核を根絶するのに必要なら、どんな手段でもとるためである」という、「“農村地帯における過激派の回教青年グループ”」と手を結んだわけが書いてあります(同 p.92)。そして虐殺のことが書かれています。これはすごいことだったようですね。ついに1966年3月にはスカルノが退陣をする。そして「…親西側の人びとで固められた正式な政府ができあがった」(同 p.93)と書いてあります。
スーザン・ジョージはアメリカの人ですが、このクーデターのことを露骨に「アメリカは再び権力を握ったのである」(同 p.93)と書いています。日本の新聞はこういうふうには書きませんでしたね。クーデターはクーデターで、アメリカが権力を握ったなんて書かずに、スハルトが権力を握ったと書いた。
それからあとの道のりもアメリカの開発を進めようという勢力が、いろいろなことをしたと書かれています。93ページの一番最後のところにある引用文は、おそらくデーヴィッド・ランソンという人の「フォードの国──インドネシアのエリートづくり」(David Ransom, ‘Ford Country: Building an Élite for Indonesia’ in The Trojan Horse: a radical look at foreign aid, by Steve Weissman and members of Pacific Studies Center and the North American Congress on Latin America, Ramparts Press, 1974)という論文からの引用だと思います。その意味するところは、要するにインドネシアで西側勢力は何をしようとしているのか。西側勢力がしようとしていることはこういうことだよと書いてあります。
「フリーポート・サルファー社…」これはアメリカの会社だと思いますが、「…は西イリアンの銅山を採掘するだろうし、インタナショナル・ニッケル社はセレベスのニッケルを獲得し、アメリカ、日本、韓国、フィリピンの材木会社は広大な熱帯林を伐採するだろう。USスチールを筆頭に巨大な鉱業会社から成る米欧コンソーシアムは…」この「コンソーシアム」というのは企業の合弁体というか、いろんな企業が寄り集まって資本を集めて企業体をつくることだね「…西イリアンのニッケルを、米英、米豪共同資本の二社は錫を採掘するだろう。また日本人はエビやマグロを持ち帰るであろう」(同 p.93)と言ったわけです。これは1965年のことです。このとおりになりました。日本人はエビやマグロを持ち帰ったし、材木もたくさん持ち帰りました。そういうことが書かれていました。
さあ、その次を続けてみてください。
フォード財団の援助を受けたハーバード、バークレー、マサチューセッツ工科大の経済学者たちは、昔仲間のインドネシア人と事務所を共同で使っている。また最後まで面倒をみる気のフォード財団は、1969年には、“インドネシアにおける外国投資家との交渉を扱えるような人材の開発”計画をつくった(同 p.94)
いろいろやり口があるらしい。おもしろいにちがいないけど、ここではそれには深入りしないとスーザン・ジョージは言っています。
さあ、みなさん、(地図を指しながら)アメリカはこんなに大きい。ニューヨークっていうのは、ここにあります。ワシントン州はどこでしょう。ワシントン州というのは、この辺にある。ワシントンD.C.というのは、どこにあるでしょう。D.C.──「District of Columbia」というのは、「特別区」と日本語では言っていますが、ワシントンD.C.というのはここにあります。小さいところです。ここにものすごい権力が集中しているんだよね。
その上のほうに行くと、フィラデルフィアとかニューヨークとかボストンとかがありますが、この辺にちょうど名前の挙がっていて東海岸の大きな大学がある。こういう大学がいろいろがんばっているやっていることは、簡単に言うと、アメリカを産業社会として世界のリーダーにするためですね。それがそういう大学の使命だね(笑い)。出てきた名前を言うと、ハーバード大学とかMITとかいろいろありましたね。(地図を指しながら)バークレーというのは、こっちのほうです。サンフランシスコの湾の反対側にバークレーという街がありますが、そこにカリフォルニア州立大学バークレー校というのがあります。
インドネシアの留学生たちはこういう大学で勉強したんだね。そういうしかけになっています。フォードというのは自動車の会社ですが、そこでつくったお金を元にしてフォード財団というのができている。フォード財団というのはとんでもないことをしたんだね。でももしフォード財団がお金をくれるって言ったら、僕らでも絶対もらいますね(笑い)。
地図を見ながらみんな考えてほしいんだけど、日本はインドネシアとどういう関係をもっただろうか。アメリカより日本のほうがずっと(インドネシアに)近いでしょう。アメリカがそんなすごいことをしてインドネシアに介入できる。日本人はデヴィ・スカルノだけかいな(笑い)。実はそんなことはない。アメリカがつくったそういうしかけに日本は一所懸命乗っかったんだよね。戦争に負ける前の日本はそういう考えかたじゃなかった。「ここ(インドネシア)は大東亜共栄圏の一部です」と言ってた。
そういうことではなくて、僕らが世界をどういうふうに見ているか。アメリカのエリートたちがこういう地域をどういう目で見ているか。そういうことをわれわれ日本の大学エリート(笑い)は、実はちゃんと知らなかった。どちらかと言えば、見ていなかったというほうが正しいよね。
ではいまの私たちはどうでしょうか。正直なところ、インドネシアがどこにあるということを、みんな本当にわかっていただろうか。『なぜ世界の半分が飢えるのか』には、インドネシア以外にも出てくる地名がいろいろあります。それを「これはどこだろう」というふうに気にしながら見てみよう。
結局のところ、スカルノは失脚をしちゃって、土地改革を進めることはできなくなってしまった、ということが書かれています。クーデターで、土地改革なんてことはとんでもない話だということになって、手に入れた土地も結局は昔の地主にまた戻ってしまった。あるいは「三〇万ヘクタールの土地が、第三者の手にころがり込んだ」(同 p.95)と書いてあります。1ヘクタールは100 m掛ける100 mだから、10,000平方メートルだよね。それに30万を掛けて、それを100万で割ると、平方キロメートルがでます。どれくらいかと言うと、3,000平方kmです。3,000平方kmって言ったらすごいですよ。100km掛ける30kmですよ。それを第三者──バークレー・ボーイズなのかな──がとってしまった、というようなことが書かれています。
日本にいるわれわれは、つまりインドネシアとは随分違う状況で、戦後の経済復興のスタートを切っています。そのなかで言うと、たぶん多くの日本の人たちはインドネシアは第三世界で間違いないと思っている。そして第三世界の開発・経済成長のためには近代化ということが必要なんだという言いかたも、たぶんそんなに抵抗なく受け入れると思うんだよね。それで「日本のようになりなさい」とおそらく言うと思います。
だけど、ここで注意をしてほしいのは、「近代化開発モデル」という言葉です。日本とはやっぱり違う。だけれども、じゃあ、インドネシアに「近代化開発モデル」を当てはめることが当然であるかのように受けとめることが、本当にいいんだろうかということを考えなければならない。
スーザン・ジョージが描いた第三世界の例──ボリビア
そのあとのページをさらに見てみると、ボリビアというのが出てきますね。ボリビアってどこだ?(地図を指しながら)この辺にあるよね。ここがボリビアですね。チェ・ゲバラっていう人知ってる? 知らないの? 毛沢東は知ってる? そうか…、知らないか。キューバっていう国知ってる? アルカイダの兵隊たちが捕まって、アメリカの海軍基地に運ばれていますね。彼らは捕虜なのか囚人なのかよくわかりませんが、そこでいま囚われていますね。そこはグアンタナモ海軍基地と呼ばれています。グアンタナモ海軍基地はどこにあるか知っていますか? グアンタナモ海軍基地っていうのはキューバにある。キューバっていうのはアメリカと敵対関係にある国なんだけど、なんでキューバにアメリカの海軍基地があるんだろう。面白いね。
さあ、そのキューバのボスは誰だろう。カストロっていう人知ってる? カストロっていう人は、なんだか最近ヒゲがどんどん長くなってきているよね。カストロとチェ・ゲバラは、ほかの同志と一緒になって、キューバで革命を起こしたんだよね。そのあと、チェ・ゲバラはキューバと袂を分かって、ラテンアメリカのほうの革命を進めにいったんですね。それで、彼はボリビアで撃たれて死にます。そういうボリビアっていう国があります。
ボリビアという国は「ここでアメリカの国防省のスローンが大いに自慢していたボリビアにおける錫鉱夫の弾圧と軍の民間活動計画を思い出してほしい。この計画は偶然の産物ではなく、一九五七年、マサチューセッツ工科大学国際調査研究所に所属していた学者たちの構想であった」(同 p.96)というところに出てきたんだね。すごいですね。つまりアメリカという国は、インドネシアだけではなくて、南アメリカ大陸のほうでもいろいろやっているよということだね。さらにこのあと読み進めると別のところも出てきます。至るところで手を出している。
スーザン・ジョージが描いた第三世界の例──ベトナム
その次のパラグラフを見てください。「…たとえばベトナムの“都市化”──農村地帯の集中爆撃で農民を都市に避難させ、それによって農民支配を容易にする──政策を押しつけるなどということが、尊敬を受けるハーバードの政治学教授にとっても、まったく“正常”な行為になってしまうのである」(同 p.96)と書いてあります。ハーバードってひどいところだなぁ、とますます偏見を掻き立てられるわけです(笑い)。ベトナムのことをちょっとしゃべらないといけないかなという気がしてきましたが、(地図を指しながら)ベトナムはここだよね。京都精華大学にはインドネシアからかなりたくさんの留学生が来ています。ベトナムからも来ています。今度しゃべってごらん。
さて、その次の行を見てください。「…政治的ヒエラルキーのなかで権力の場を得た“ニューフロンティア知識人”にとっては、戦争で残忍な手段を提唱することも正常なことになる」(同 p.96)と書いてあります。さて、「政治的ヒエラルキー」ってなんですか? 「政治的ヒエラルキー」というのは、ピラミッドのようなものがあって、ちゃんと階級がある。上のほうの階級が下のほうの階級を支配している。そういうのを「ヒエラルキー(hierarchy)」って言います。
では、「ニューフロンティア知識人」ってなんですか? 「ニュー(new)」っていうのは「新しい」っていう意味だよね。「フロンティア(frontier)」というのは「開拓」ですね。「ニューフロンティア」ってなにか。アメリカのフロンティアは、アメリカ東海岸にヨーロッパのほうから船で来た人たちが住みついて、そこから南のほうに行ったり、ミシシッピ川を越えてさらに西に進んだりいろいろして、(アリゾナ州、ニューメキシコ州あたりを指して)このへんでアパッチ族と戦かったりしながら、ついに西海岸に辿りつく。その過程でスペインを追い出したりとか、そういうのを「フロンティア」って言うんです。「開拓物語」だね。
「ニューフロンティア」っていうのは、もう(アメリカの「フロンティア」は)西の端まで行っちゃったから、あとは南のほう(南アメリカ大陸のほう)へ行ったり、インドネシアのほうへ行ったり、ベトナムのほうへ行ったりということですね。こういうのを「ニューフロンティア」って言うんですね。要するに、経済開発というようなことを、あるいは「フロンティア」の過程で自分たちがつくったアメリカの自由な産業的社会をさらに世界におし進めていくという考え方をもっている「知識人」のことだね。「戦争で残忍な手段を提唱することも正常なことになる」というのは困ったことですが、そういうふうにスーザン・ジョージは言っています。
スーザン・ジョージが描いた第三世界の例──カンボジア
さらにその次を読んでみましょう。「カンボジアとチリのような国に深く介入したキッシンジャーもかつてはハーバード大学の教授であった」(同 p.96)と書いてあります。キッシンジャー(Henry A. Kissinger, 1923−)って知ってるかい? 知らない? キッシンジャーっていう人はノーベル平和賞もらったんだよ。佐藤栄作っていう人も実はノーベル平和賞もらったんだよね。知ってますか、みなさん。
キッシンジャーがノーベル平和賞をもらったのは、ベトナム戦争を終結させたっていうことだね。アメリカが手を(ベトナムから)引く──手を引いたんだから別に誉めなくてもいいように思うんだけど(笑い)──秘密交渉をレ・ドクト(Le Duc Tho, 1911-1990)というベトナムの偉い将軍とやった。それでノーベル平和賞もらったんだよね。それからニクソンが中国と国交回復をしますね。そのときにもキッシンジャーがその水先案内というか、事前に中国と秘密でいろいろ接触をして、ニクソンがそういう舞台に出られるようにした。そういう人です。もともとドイツで生まれた人ですが、たぶん1930年代(1938年)にアメリカに移民をしたんだね。いまでも健在ですよ。キッシンジャーの有名な言葉に「権力こそ最高の媚薬である」というのがあります。「媚薬」っていうのは、興奮する薬ね。
カンボジアがなんでここで出てくるかと言うと、ベトナム戦争で当然となりの地域もいろいろ戦争が起こるわけですが、(アメリカは)それに介入するんですね。その介入のあとカンボジアがどういう状況になっていったかというのは、たぶんみなさんが知っているとおり、ますます左の勢力がある種の「原理主義化」していくんだね。そういうことが起こりました。ちょっと「原理主義化」という言いかたはよくないかもしれませんが、ポルポト以前の状況をここでは指しています。
スーザン・ジョージが描いた第三世界の例──チリ
それから「チリのような国に深く介入した」というのはどういうことかと言うと、サンティアゴっていうのを知ってるかい? チリっていう国はどこにある?
中尾:佐々木くん、チリはどこだ?
佐々木:アルゼンチンの西
中尾:(地図を指しながら)これだね。このめちゃくちゃ長い国、これがチリです。
それで、チリという国でなにが起こったか。みなさんは少しは知っていると思うんですが、ピノチェト(Augusto Pinochet Ugarte, 1915‐)という人を知ってる? この人がイギリスでどういうわけかイギリスの警察に身柄を拘束されて、スペインが「ピノチェトをスペインに送れ」という要求をする。けれどもイギリスはスペインの要求どおりにはしなかったというような出来事があったよね。結局、ピノチェトはチリに送り還されますが、送り還されたときにはもう痴呆の老人になってしまっていて、もうこれは裁判にかけてもどうしようもないということで──まだ生きてるのかな。死んじゃったかな(2002年12月時点では健在)──いまもうあまり問題にもされなくなった人ですが…。世界中のスペインのような国、あるいはその他の国々からピノチェトは犯罪者であるというふうに言われているんだよね。ピノチェトという人は、1972年にアジェンデ(Salvador Allende Gossens, 1908−1973)というその当時のチリの大統領をクーデターで倒した。それ以来、チリでは恐怖政治がしばらく続くんだね。サッカー場の大虐殺とかいろんな出来事があります。
どうしてチリとキッシンジャーが関係あるかと言うと──アジェンデのことはたぶんこの『なぜ世界の半分が飢えるのか』のなかにも書いてあったと思いますが──アジェンデ政権は農地改革などいろいろなことを考えるわけですが、さっきのインドネシアと同じように外国資産を国有化するという政策をもったんだね。4回目の授業のときにITTの話をしたでしょう。「情報伝達技術」というのを全部言うとITTになるけれども、ITTというのは「International Telephone and Telegraph」の頭文字だよと話しましたよね。ITTっていうのは、アメリカの会社で、日本で言うとKDDみたいなもんですよ。しかし、通信会社は通信のことだけやっているわけではなくて、いろんな仕事ができますね。なんでもしていいんですよ。おもしろいですよ。私企業っていうのは、なにしてもいいんです。
それで、アメリカはまずITTの利権を守らなければいけない。…
…ああ、もう時間がきてしまった。(授業終了のベルが鳴ったのを聞いて)終わっちゃった。どうしようもないね…。
要するに、露骨に言うと、社会主義だとか──つまり私企業がなんでもやっていいというようなことを認めないような政治──がチリで確立されたら、「もう南アメリカ全部あるいは中米まで含めて、自分たち(アメリカ)が影響力を及ぼすことができない地域になっちゃう。さらには大西洋を越えて、ラテン系であるイタリアあたりも全部共産化するぞ。それはなんとしても阻止しないといけない」ということで、キッシンジャーは秘密にピノチェト──彼は軍隊を仕切っていた男ですが──に金を流すとか、CIAに活動するように命令を出すとか、いろいろするんですね。チリとキッシンジャーはそういう関係があります。
こんなことやっている(こういうペースで進んでいる)と全然ダメですけど、これは冬休みの宿題にするしかないね。みなさんが授業で取り上げた本を読まないとレポートを書けないような状況をつくっていく、ということをちょっと考えています。
今日は取り上げられなかった『なぜ世界の半分が飢えるのか』5章の「緑の革命」の部分を読むと、またまた驚くようなことが書かれていて、みなさんは肝を潰すかもしれませんが、まあ、お読みください。次回もまだスーザン・ジョージをやります。
これで今日の授業は終わりです。
- 注1:
- 中尾ハジメは、この授業が行われる2週間ほど前(2002年11月29日)に京都精華大学で行われた『新しい大学の使命』と題されたシンポジウムの論者のひとりとして参加した。このシンポジウムは新学科開設記念講演会のシリーズ第4回で、論者は他に上野千鶴子さん、苅谷剛彦さん、橋爪大三郎さん、そして司会が西研さんでした。
参照リンク
- Transnational Instituteのページのなかにあるスーザン・ジョージのページ
- TRANSNATIONAL INSTITUTE HOMEPAGE SUSAN GEORGE
- 「フォード財団」
- Ford Foundation
テープ起こしをしたひと: 川畑望美