
爆心地から1.4マイル(約2.3Km)の広島御幸橋(1945年8月6日 午前11時)
写真:広島平和記念館
私は重松家と親しくしている井伏の生家の当主・井伏章典氏の案内で、平成九年四月以来たびたび小畠の重松宅を訪れ、欄外に書き込みの多い日誌原本四分冊を閲読する幸運に恵まれた。しかし閲読しているうちに、広島の原爆被災記録としても、また「黒い雨」解読の必見資料としても極めて重要な記録文書であることを確認したので、これの活字化を夢想するようになり、何度か重松家の当主夫妻に「重松日記」の出版を進言して来た。その結果、昨年の五月に了解が得られたので直ちに原本の浄書に取りかかり、脱稿後原本との照合を行なった上で筑摩書房へ送って検討してもらい、『黒い雨』上梓から三十五年目にしてようやく陽の目を見ることになったのである。改めて重松文宏・フミヱ御夫妻の理解ある決断に敬意を表する。
相馬正一「解説」(『重松日記』筑摩書房、2001)より
■レポートの書き方について
中尾ハジメ:前回、レポートを出していただきました。まだ読みきれていないんですが、なかなかちゃんと書いてあるな、という感じがします。しかしレポートを読んでいて気がついたことをいくつか言います。一つは、この授業で使った資料を見てるものだから、わざわざどの資料を見て考えたとか、あるいはどの資料にこういう個所があったということは書く必要がない、と皆さんが思っているようですね。しかし習慣にした方がいいことがあります。つまり「注」をつけるということです。その「注」が、いわゆる「文献の注」みたいな形になっていた方がよろしいです。そういう書き方を覚えてください。中にはそういうふうに書いている人もいました。つまり「参考資料」という形で挙げていた人も数名いましたが、自分の文章の中に「注」をつけて、この部分は誰が主張してることなのか、ということを丁寧に区別して書いた人はいませんでした。これはやってください。いわば「レポートの作法」みたいなものです。
次の問題。何かを表現しようとしているのは分かるのですが、例えば「バーチェットがアメリカ人だ」というふうに書いている人がいました。が、バーチェットはアメリカ人じゃないよ。カタカナ名前が出てきたらアメリカ人だと思ってもらっては困る。それからバーチェットに絡む話ですが、ニューメキシコの砂漠で原爆実験をしますね、それを取材したのはバーチェットではありません。それを取材して、バーチェットの目から見たら問題のある記事を書いた人はウイリアム・ローレンスという人です。それは読んだら分かるはずなんですが……。どうもそういうように読んでないという人が数名いました。
それからもう一つは、時間の経過というのが──これもバーチェットに絡むことですが……。バーチェットが『広島TODAY』を書いたのは、原爆投下からずっと後になってからだよね。『広島TODAY』の中にでてきた、ニューメキシコでの実験は広島以前の話です。もう一つはバーチェットの書いたものの中に、それからもっとあとの1950年代の話もでていたと思います。書く人は当然のことながら──映画で言ったら「カットバック」みたいに──昔のことを書いたり、もっと今に近いところを書いたり、それからもう一度昔に立ち戻ったり……そういう書き方ができるよね。それをちゃんと読み取らないと、なんだかおかしなことになっちゃいます。
それからアメリカをいっしょくたにして、これは「アメリカ対日本の話」で、ひとまとめにして「アメリカ人はこう思っている」、「日本人はこう思っている」という言い方をする人がいました。まず、そんなふうにまとめることはほとんど不可能だよね。レポートを読んでいて目についたことをいくつか言ってみました。
全体としては、皆さん、自分のとらえ方を比較的正確に書いたレポートが多いかったと思います。誰かから借りてそれを書き写したようなものは……3つぐらいはあったかな(笑い)。他の人たちのレポートは、ちゃんと自分で書いているな、とわかるようなものでした。
■『黒い雨』と『重松日記』
今日の授業も、あっちにいったりこっちにいったりすると思いますが、今日で「原子爆弾をめぐるジャーナリズム」というのは、いちおう終りにしたいと思っています。リチャード・ローズについてしっかり掘り下げられたかというと、たいへん疑わしいですが、次回からは素材としては今まで皆さんに見てもらったものを使うかもしれないけれど、もう少し原理的な問題について考えたいと思います。つまり、「科学と事実」というようなこと──ひょっとしたら「事実と虚構」という問題に入るかもしれません。しかし今日はもう少し「原子爆弾をめぐるジャーナリズム」にこだわってみましょう。
今日の前半は『黒い雨』と『重松日記』を取り上げて少し話をしてみたいと思います。読んできたよね。読んできた感想など、いろいろおうかがいしたいところですが、ちょっと時間がないのでそれはできません。みなさんの資料には、奥付けがあると思いますが、『重松日記』のいわば「解説」、あるいは「あとがき」にあたるものです、書いた人は相馬正一さんだね。結局いろいろ探してみましたが書いてあるものとしては、相馬さんが書いたものに依拠して説明することが適切だろうと思いました。『重松日記』と『黒い雨』の関係については、いろいろなことが言われています。井伏鱒二を批判する議論がどちらかといえば多い。しかしながら相馬さんが書いたものを見ると、そうは簡単に言いきれないという感じがよく分かるものだし、今ここで皆さんに相馬さんの文章を見ていただくのは、井伏鱒二はいいとか悪いとか、というような問題ではなくて、そもそもジャーナリズム、あるいは言論表現活動というのが実際どういうふうに行われているかということを、よく皆さんに知っていただきたいということが主眼なのです。
■相馬正一さんによる「解説」(『重松日記』)を読む
奥付けをちょっと見て。2001年5月25日の発行になってますね、著者を見ると「重松静馬」というふうになっていて、当たり前といっちゃあ当たり前ですが、重松静馬という人は、下を見てもらうとわかるように、昭和55年10月19日に亡くなっています。昭和55年というのは西暦になおすと何年ですか? 1980年だから、ご本人が亡くなってから20年以上経って、本になって出版されて、著者は重松静馬。……そういうふうになっていたね。その下にですねCを○で囲んであるでしょ。このCはCopyrightのCですね。著作権が誰にあるのかということを記しておりますが、「2001 Fumihiro Sigematu 他」。「他」だけ漢字で書いてあるけど、重松文宏さんたちが著作権を持っていることが記されています。重松文宏さんという人はどういう人かというと、重松静馬の次の代の重松家の当主であると説明があります。息子さんにあたるのかな? 「息子かどうかなんてことはどうでもいい」などとは思わないようにしてください。細かいことかもしれませんが、ジャーナリズムとか、あるいはもっと広く言論表現活動が行われるのは、それは現実の社会の中でしかないということが大事だと思います。皆さんは井伏鱒二の『黒い雨』というものがどんなものなのかは、だいたいのところは読んだよね。全文をくまなく読んだのではないのだけれど、その部分をサンプルとしてもっているわけですから、どんなものだか知っていると思います。それと同時に「重松日記」がどういうものであったかを照らし合すことができるように、皆さんは資料をもっています。相馬さんは「解説」で、276ページの下の段の真中辺りで、「重松日記」と呼ばれているものが、どういうものであったかを説明しています。
現在欄外に書き込みの多い『重松日記』の原本は四百字詰原稿用紙に書かれた四分冊(本編二冊続編二冊)となって重松家に保存されている。その内訳は、一冊目の火焔の日が八月六日から八月十日まで百二十八枚二冊目の被爆の記が八月七日から八月十三日まで百三十九枚三冊目の続火焔の日が八月十一日と十二日の三十枚、四冊目の続被爆の記が八月十四日と十五日の二日間及び後期の七十八枚で単純計算すれば三百七十五枚となる。ただし本編二冊には八月七日から十日までの項に重複箇所が多い。
本のタイトルは『重松日記』なんですが、もともとの原本があると書かれています。こんなに枚数についてくわしく書いてどうするのか、と思うのかもしれませんが、あらためて整理をするためにどうしても必要だったのですね。つづけて読んでいくと、次の段落の3行目に「8月6日午前8時15分前後から書き出された物で」と書いてありますが、これは「その時から書き始めた」という意味ではありません。「8時15分前後からの自分の体験を書き始めたよ」という意味です。「火焔の記」、これが128枚あるんですけどれども、そのうち80枚が8月6日にあてられている。
眼前に広がる広島郊外の無残な光景と重松一家の三人の命懸けの逃避行が重松の目を通して即物的に記録されている。
というふうに書かれています。繰り返して言いますが記録されていると書かれているけれども、これは走りながら逃げながらそこで記録したのではない。後になってから書いたものだね。その後さらに、ここで
四十八枚に八月七日から八月十日までの四日間における重松の見聞が記録されているが、こちらのほうは初日の<死線上の彷徨>を脱して3人が古市町の繊維工場に辿り着いた翌日からの記録である。
と書かれている。こういうふうにですね、「仕分けをする」という仕事をまず相馬さんがしているということに注目してください。 ……それに対してというような文章がつながっていますが、真ん中あたりかな。
しかし<被爆の記>の本命は八月十一日から十三日までの三日間の記録で、これには七十二枚を充てている。
で、そこの一番最後の行ですが、
本書では重複箇所の加除訂正を確かめるためにも本編双方の全文を収載した。
つまり重複があるということ。本編は2つあるのですが、それは両方とも全文を載せてあります。下の段にいくと
一方、続<火焔の日>は照合の結果、本編<被爆の記>の八月十一日と十二日の二日間の浄書稿と判明したので掲載を見合わせた
これは載せてないってことだね。その後の<続被爆の記>は載せてあるんですが、それについてもそういうふうに書かれてあります。その次、ここをよく見てください。
重松は被爆の翌日から、自ら体験し、あるいは見聞した被爆状況を手帳<当用日記>にメモしており、帰郷後にこのメモに基づいて昭和二十年九月から断続的にノートを執っている。
まずメモがあった。それから一月程たってからそれをノートに書き始めた。それからその次に
しかし、本格的にこれを記録として書き残すことを思い立ったのは、それから四年後の昭和二十四年である。
1949年のことである。1949年というのは、今まで皆さんが知っているものから考えればどういう時間の流れかというと、ジョン・ハーシーによって書かれた「ヒロシマ」が日本語に翻訳され出版される年ですね。それから278ページ、上の段ですが──その間ノートをとっていたわけですね。ノートをとって昭和24年になったら本格的にこれを書き始めた。おそらくこれは原稿用紙に向かって書いたものだと思いますが、
昭和二十四年になったら連日自宅の小部屋に閉じ籠り、二年がかりで本編の<火焔の日>を書き上げ、この二冊分を手文庫にしまいこんだまま入退院を繰り返していたという。
小部屋に閉じ籠って2年がかりで書いたんですね。それから次の段落へいってください。
前回書き残した八月十四日と十五日正午までの記録の執筆を思い立ったのは、本編二冊分執筆から十年後の昭和三十四年である。
さらに十年が経過しています。
手帳のメモを辿りながら、その年の十月頃から書き始めて翌年の一月に脱稿している。
■10日間足らずの出来事を15年間かけて描いたこと
結局のところですね、昭和20年9月──皆さんも読んだと思いますが──子供たちに宛てて書いた文章から数えて15年の歳月をかけて、ようやく書くべきことは全て書きつくしたのであろうと相馬さんはまとめています。さあこれで、どういうふうに表現したらいいのかなかなか難しいのですが、時間がこれだけかかっている。ただ単に時間が流れたのではなくて、その間重松さんは病院に出たり入ったりということが片一方であって、しかし小部屋に閉じ籠ってとにかくこれを書き続けたんですね。皆さんも分かるように、そこに書かれてある「体験の時間の長さ」というのは、8月6日から15日でしょ。日数にしたらわずかです。それを原稿用紙に向かってこれだけの時間をかけて書いた。もちろん書いてない時間もあったに違いないけれども、しかしそうしないとできなかったんだね。それだけの時間がかかっている。というわけでございます。これを皆さんはどういうふうに感じたか分からないけれども、自分が体験した大変重要なことを記録に残そうとすることに、これだけの時間がかかった。……かかるものです。さらに井伏鱒二が、重松さんが書いた日記を見てそこから何かを作り出したのですね。それにかかっている時間は、重松さんがかけた時間からみたらそれほど長くはありません。長くはないけれども、それでも時間はかかる。皆さんがレポートを書くにも時間がかかりますね。これは時間をかけて書かないと書けない。頭の中で考えてるだけでは書けない。
■『重松日記』誕生のプロセスを追う
これは授業の最初ぐらいに言ったと思いますが、ジャーナリズムという言葉だけで考えたら時間のことを考える必要もないし、物理的なさまざまな問題──例えば、印刷しなければならない、本を作るのに紙がなければならないとかいうようなこと──があると言っていたと思いますが、具体的に言うと例えば、重松さんがこれを書くのにどれぐらいの時間がかかったか。それから、その後に井伏鱒二がそれに手を加えて『黒い雨』を出版をするわけですが、出版というものの世界の中でやっぱり同様だということに注目してください。278ページの下のところですが、
重松の被爆日誌はあくまでも<子孫のために>書かれたもので、脱稿した昭和三十五年一月十日の時点では井伏に送付して読んでもらうことなど、毛頭考えていなかった。
とあります。279ページに書かれていることは、これはもうすでに前回か前々回に言ったことでありますが、つまりいろいろなことが時間を経てわかるようになってきたんですね。わかったことをもとにしてまた自分が体験したことを書こうとすると、体験した当時の認識とは違うことを書かざるを得なくなります。体験とは奇妙なものですが、そういうものです。これも実は重要なことなので、覚えておいてください。さて、次の2枚目の表のほうですね。280ページのところを見てください。上のほうに、これは前のページの279ページから続いていますが、朝日新聞の記事ですね。仁科博士らの研究グループの災害調査委員会の報告書が出されています。これはちょうど原爆が落ちてから一月ぐらい後のことです。それを見てまず重松がどういうふうに考えたかのであろうということを、相馬さんが書いている。主語がいっぱいあるから気をつけてくださいね。相馬さんが書いているところを読むと、
学者による楽観的な災害状況の発表は一般の人々に被爆の危機が去ったかあのような印象を与え、広島・長崎以外の土地の人たちはいつしか原爆の記憶から遠ざかるようになってゆく。重松が被爆体験を本格的に記録しようと思い立った背景には、自ら視線を彷徨した原爆地獄の実態がともすれば風化しそうになることへの危惧と・・・
云々書いてあります。繰り返して言いますが、昭和20年、1945年の9月におそらく重松がそういう動機を持っただろう、と相馬正一さんが書いているんだね。しかしそれ以降どれぐらい時間がかかったかというと、15年。それだけかかったということは、先ほど言ったとおりです。
・重松静馬と井伏鱒二のやりとり
さてその同じページの下のほうですが、「『黒い雨』成立の経緯」というタイトルがついています。
重松が被爆日誌を戦後に釣り仲間として知り合った井伏鱒二に見てもらおうと考えたのは、浄書脱稿から二年半たった昭和三十七年たった六月のことである。
昭和37年というのは、1962年ですよね。重松と井伏鱒二がどういうようなやり取りをしていたかということがその書かれています。井伏鱒二はご存知のように小説家、文筆家、文学者だね。それでいろいろ自分が書く素材を探すことがあったと思いますが、重松さんの案内を得て古文書などを手に入れていたらしいということが書かれています。で、その縁で──今度は281ページの上のほうの真ん中辺りから
仲間と相談して胡桃を植樹した岡(城山植物園)にも標石を立てることを決め、再び碑石文の揮毫を井伏に依頼するが、その依頼状(昭和37年6月26日付)の後半に被爆日誌のことを書き添えた
「揮毫」というのはようするに、筆で字を書いてもらってその字を石に彫るんですね。そういうことを(井伏鱒二に)依頼したんですね。
・「自分がやらなければいけない」という想いを持つ
次に私こと広島原爆被災の日より十五日終戦正午迄の被爆日誌を記して子孫に残す可いたしておりました。その内容は被災逃避、市内の状況、郊外の情状、植物、動物、<雀、はと、犬、猫、魚類>等、眼に映りましたものをそのまゝ記しております。そしてノートより原稿用紙に浄書いたしました処、二百五十余まいとなりました。
それから、原水爆禁止のことがちょっと書かれていますが、282ページの上の段2行目から
これは第五回世界原水禁大会(注、昭和三十四年八月六日)に郡代表として出席いたし、多くの他府県の代表とお会い致し、余りにも事実認識無きにがっかりいたしました。
そこから、これは自分が日記を書いて子孫に残すだけでは不十分で、もっと違う使い方があるという考えに及んだと思います。同じ上段の後ろから3行目
被爆記録もたく山世に出て居り、もはや時期はずれの感がいたしますが、一生の御願いでございます
何らかの形で世の中に文筆してこれを井伏鱒二が発表してほしいというふうに言っております。282ページの下のほうを見ると、この手紙を読んだ井伏鱒二が8月2日付けで、重松さんに葉書を書くんですね。それで被爆日誌を自分のところに送ってくださいというふうに伝えたわけですが、その葉書を読んだ重松さんは
重松の<当用日記>によると、七月四日に井伏の葉書を受けとった重松は、改めて浄書した被爆日誌を読み返してみると<どことなく線が細い>ことに気づき、<再び原稿用紙の整理>に取りかかる。<当用日記>には<一日中原稿整理>の文字が七月四日から七月九日まで毎日のように記載されており、前年の三月に結婚して同居していた重松文宏・フミヱ夫妻の話によると、重松は奥の小部屋に閉じ籠り、昭和二十年八月六日から八月十五までの記録を推敲した上で、最後に<被爆其後のことども>を書き加えていたという
という作業がここであったわけです。
・重松静馬と井伏鱒二のやりとり<その2>
さて、これに対して井伏のほうはどういうふうにそれに応じていったかということがその後書かれています。283ページの上の段後ろから3行目ぐらい
小説の<材料としての非常に食手《←手は井伏が書いたまま》が動>いたにも拘らず、実際に体験していない空前絶後の大惨事なのでこの記録を使って創作することが億劫になり、そのまま預かっていても「宝の持ち腐れ、または犬がおあづけをくつたやうなもの」だから返却したい旨の手紙を重松へ送る。これに対して重松から、返すに及ばないからお手許に置いて御随意に利用して構わないことと、そのことで調査することがあれば遠慮なく申し付けてほしい旨の返信があったので、井伏は再び日誌を素材にして創作することを思い立ち、早速重松に対して現地取材の協力を依頼したことに至っております。
つまり、重松と井伏の間には さかんにやりとりがあったんだね。
・出版をする
それだけではない、当然のことなのですが、これも非常に重要なのことなので考えていただきたいのですが、──考えるまでもないかもしれませんけども──ハーシーの時にもこれは編集者がいて、それからその週の週刊誌に全面的に「ヒロシマ」の記事をだすという決断をした、あるいはそれを売ろうという出版社、雑誌出版社があったんだね。あるいは社長さんがそういう決断をしてそれが実現するようにいろいろ努力する。で『黒い雨』の場合は、
一方井伏は創作過程で日誌に書き込みをする必要があるので、連載を依頼して来た『新潮』の斎藤編集長に資料の買い取りを持ちかけ、了解を得たので重松に日誌借用の謝礼(買い取り金額)と作品に実名を使用することの可否を手紙で問い合わせた。
というふうになっております。で今度はそれに対して重松の返答があるんですが。284ページの上の段の後ろから3分の1程度のところに、
確実にお答え出来ますことは、先生のお筆で私の実名(愚妻)も使ってお書きすることはよろこばしく、亦永久に記念になりますので、どうか実名御使用御執筆の程を御願い申上げます。
というふうに書かれております。
284ページの後ろから3行目あたりには、新潮社が重松さんに払った金額が書かれています。
現在の物価に換算すれば百五十万円位
そのお金で重松さんが何をしたかということはほとんど資料に書かれております。
・「ルポルタージュ風」にならざるをえなかった主題としての出来事

さて286ページこれは前のページからの続きですけれども、井伏鱒二が重松さんに向かってではなくて、いわゆる世の中というのかな言論家、あるいは評論者、表現家に向かってしゃべっているんですね、『赤旗』と言うのは知ってるよね。共産党の機関紙ですが、『赤旗』のインタビューに応じてこういうふうに語っています。 286ページの上段の真中あたりですが、
あの出来事は空想で書けるというようなものではなかった。空前絶後の問題だった。それであんなルポルタージュ風のものになった。
と書かれています。みなさん奇妙に思うかもしれませんが、「ルポルタージュ風のもの」なんです。しかし、ルポルタージュではない。それからその後『黒い雨』というタイトルがあるんですが、その黒い雨にあたったという人物についての言及があります。286ページの下の段ですが、談話の中の「その人のめいにあたる」──その人とは重松さんのことなんですが──「一七、八歳の少女」が「黒い雨にあたった」というのは、「井伏の思い違いか作り話である」というふうに相馬さんは言っております。で、おそらくそうなんでしょう。
・「泥棒を見てから縄を結う」ようなやりかたの薦め
それでもう少しおもしろい表現があるので見ていただきたい。287ページですが、これは人によっては、こういう書き方をすることは、井伏をけなしているんであろうと、思う人がいるかもしれません。が、ぼくにはそういうふうには読めない。そこを読んでみますね。287ページ上段の上の方ですが、結局そのめいごさんの日記がないことが分かる。連載をしているわけですが、途中でいろいろ作戦を変えなきゃいけなくなってくるんですね。で、その結果、作品に矛盾があるというようなことを言われても仕方がないことが、起こってまいります。後ろから4行目かな。「つまり、井伏は『重松日記』をベースに据えて、『姪の結婚』の連載を始めたものの、高丸安子の病床日記が処分されていたのを知った時点で急遽方針を変え、重松に新しい調査を依頼して資料を収集しながら」──僕はここに注目をしましたが──「半ば泥縄式に書き進め……」。泥縄っていうのはたいてい悪い評価ですね、「そんな泥縄式はやめなさい」というように使うんですが、泥縄式以外に行き方がないと思う。我々としてはここでいたく感激をして、あーそうか、やっぱりそうかーと思うわけです。
連載途中で「姪の結婚」を『黒い雨』に改題後も重松のセットした場所に赴いて取材活動を続けるなど、かつて経験したことのない苦渋を強いられていたようである。
創作というのとは違うんですね。でも、「創作すりゃいいのに」とも思わないわけでもない。しかし、それじゃあいけないと、思ったんでしょうね。たいへん苦労したということが書かれている。というか相馬正一さんはそういうふうに考えております。井伏はここで苦労したというふうに相馬さんは考えております。
現存の二人の往復書簡を見る限り、『黒い雨』が文字どおり井伏と重松の二人三脚で書き進められて行った経緯がよく判る。
というようなことが書いてある。で次ページ。結構時間がかかるなあ。
286ページの上の段ですが、結局ですね、井伏は『黒い雨』の初出稿、一番最初に出した時の原稿を書きなおしたんですね。そこに手を入れて、全21章を20章に組み替えた。それから若い人たちにも読んでもらえるように、初出稿の歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに改めて単行本『黒い雨』を上梓したのはいつであったか。昭和41年、1966年のことですね。ということはですね。重松が井伏鱒二に手紙の中で、自分がそういう日記を持っているということを書いてから4年が経過しております。
・『重松日記』出版へ
 で、その後、軍医の岩竹博さんという人の手記について、相馬さんが語っている……。ここの中にも注目すべき点がいくつかありますが、それは飛ばしてしまいます。飛ばしてしまって、291ページ上段をちょっと見てください。今度はですね、相馬さん自身が、なぜ自分がこの『重松日記』を本にして世に問うということをしようと思ったのか、ということが書かれております。彼は重松宅を訪れて、
で、その後、軍医の岩竹博さんという人の手記について、相馬さんが語っている……。ここの中にも注目すべき点がいくつかありますが、それは飛ばしてしまいます。飛ばしてしまって、291ページ上段をちょっと見てください。今度はですね、相馬さん自身が、なぜ自分がこの『重松日記』を本にして世に問うということをしようと思ったのか、ということが書かれております。彼は重松宅を訪れて、
欄外に書き込みの多い日誌原本四冊分を閲読する幸運に恵まれた。しかし閲読しているうちに、広島の原爆被災記録としても、また『黒い雨』読解の必見資料としても極めて重要な記録文書であることを確認したので、これの活字化を夢想するようになり、──活字というのは要するに「本にする」ということです──何度か重松家の当主夫妻に『重松日記』の出版を進言して来た。
平成9年というと何年ですか。97年?──難しい国だね日本は(笑い)。キリストの生誕からの西暦と一緒に考えねばならない。今年は平成14年、2002年ですから、2002年から5年ひくと──97年から相馬さんは重松さんの家に行って、この日記を見ていた。そこから数えると、6年かかって本になったということですな。今度は筑摩書房が登場してきますが、筑摩書房にそれを送ったんですね。
『黒い雨』上梓から35年目にしてようやくである。『重松日記』が陽の目を見ることになったのは、『黒い雨』上梓から35年目にしてようやく陽の目を見ることになった。
で、その後の2行
改めて重松文宏・フミヱ御夫妻の理解ある決断に敬意を表する。
とも書かれています。文宏さん、フミヱさんがこれを活字にして、つまり「本にしていい」「本にして下さい」というふうに決断しなければ、我々はこれを読むことはなかった。ということでございます。
えー、なんかあんまり凹凸のない話のように思うかもしれませんが、繰り返して言いますけど、これだけ時間がかかった。でこういうふうに時間がかかったことは、「けしからん」とかなんとか言ったってしょうがないことなんですね。かかったんですよ。かかってもそれをしなければならなかった。しようとした人がいるんですね。それも一人じゃない。重松自身もそうだ。井伏ももちろんそうだ。それを見た編集をする人、それから出版社。で、当然出版社というのは自分が印刷するわけじゃないですから、印刷屋さんが印刷しないといけないんですね。で、その頃は今みたいな印刷ではなくて、活版印刷だったんですね。……ということ全てに、やっぱり時間がかかっている。そういうことを、読み取ってほしい。ほとんどこのことだけ着目してくれたらいい、って感じもするくらいです(笑)。どちらかというと、『重松日記』と、井伏鱒二が書いた『黒い雨』の間の差が何であるかということは、あんまりたいした問題じゃない。というふうに私は思っております。
■「伝える」という言葉でジャーナリズムを表せるか?
さて、本当はもっといろいろ言わないといけないんですが、来週の予告編をしたいと思います。来週は前回渡しておいたやつだよね。リチャード・ローズという人の『原子爆弾の誕生』からいくつかひろってきて、それを資料にしました。それからもう一つは、H. G. ウェルズの『解放された世界』からも3ヶ所ぐらいだったかな。それも抜粋をして、資料にしております。とにかくそれをよく読んでおいてください。
これまでは、何をしてきたかと言うと、原爆が落ちて、それで被災をした人たち──多くの人は死んでしまったのですが──生き残った人たちの体験がどんなふうにして伝えられたかということに焦点がありました。で、皆さんがもし丁寧に読んだとしたら、ただ何か体験や事実が伝えられたとか、報道が伝えられたということではなくて、もう皆さんが生まれるはるか前のことだったけれども、ある種その体験を共有する、つまりただいわゆる知識として知ったということではないというふうに感じると、思うんです。それをどういう言葉で言っていいか──ちょっとなかなかいい言葉が見つからないので、言いませんが──言葉がない。どうも無いようです。あえて言うとこれもおかしいが、おかしいんですけどね。体験を共有することがあります。そういう感じもします。しかし普通はそうは言ってこなかったんですね。だからやっぱり「伝える」とかそういう言葉で言ってきたと思うんですが、読者である我々の側からすれば、何と言ったらいいか。「伝えられた」というのかな。あんまり僕はそういうふうに感じておりません。「伝える」とか「知らせる」ということで、充分言い表せているか、これは言葉の問題として相変わらず問題は残っております。
■現実の状況との緊張によって形作られるジャーナリズム
それからまたちょっと後戻りしますが、結局そのことを書いたバーチェットにせよ、ハーシーにせよ、それからほかにも、直接的にそれを体験してそれを時間をかけて、いろんな形で表現をしていった人達、そういう人達は例えば──あんまりこれだけにピントを合わせるのは、面白くないと思いますけども──「プレス・コード」のようなものあるいは、その他の社会的な現実の状況の中で、その現実の社会に向かって、発表するという「緊張」というか、「課題」のようなものをずっと持ち続けた。あるいは持ち続けるということを考えねばならなかったかもしれませんが、それが無ければ結局のところはジャーナリズムは形をなさなかったんですね。そのことに着目してほしい。書かれたものは、ただ活字がそこに並んでいるだけではないことは、みなさんが読んだなかで分かったと思います。しかし、そこで読まれた中身以上に、そういうものが出回ったということ。その出回らせるように努力をしなければそんなことは実現しなかったんだよね。それがどういう種類のものだったかは、そこの文字の中には書かれることはまずありません。まず無いけれども、出版にかかった時間であるとか、いろんなことを考えてみれば、皆さんにもそれは十分想像できると思います。そしてその仕事があってはじめて、時間を超えて、あるいは空間を越えて、我々が共有するということをした。それが片一方にあった。
■原爆を落とした側の「出来事」は共有されたか?
しかしよくよく考えてみれば、たとえばトルーマン大統領のその当時の声明文を見て、われわれが垣間見た別の側面があります。それは当然ながら、原子爆弾が爆発をして、そのことによって死んだりあるいは生き残ったりした人たちの視点ではなく、全く別の角度をもった視点と考え方といいますか、そういう世界も存在している。それがなければ原子爆弾が広島の上空で炸裂することもなかったわけでね。その原子爆弾をいったい誰が、どういうふうにしてこの世に存在させることになったか。このことを誰が記録をしたのか、誰がそのことを振り返って、さっきの言葉で言うと、我々の共通の体験にするという作業をしたか。これが驚くほど少ないです。なんでなのかなと未だに私は不思議と思ってるんですけど、恐ろしく少ないです。
断片的には色々ある。原子爆弾の技術にかかわる──それはほかでもないそれは核分裂による連鎖反応をどうしたら起こすことが出来るという科学の歴史。これはあります。だけどもこの科学の歴史はどうもなんか遠いんだよね。さてトルーマン大統領のあの声明というのは──これもちょっと細かいこと言いすぎてみなさんは何を言っているのか解らなくなるかもしれませんが──みなさんが資料をみて解ったことは、6月の29日にはすでに文案が作られていた、という類のことだよね。何処に落とすか、というのは選択肢がいくつかあってはっきりはしてなかった。長崎は選択肢のなかにすでにふくまれていた。それから何月、何日、何時ということも、だいたいこのあたりということは考えられていたけれども、まだ決まってなかった。けれどもこれも非常に露骨に、この声明文の原稿は、原爆を投下してからもしそれが成功すれば、数時間以内に発表するべきものというふうに想定をされて書かれている。さらにその声明文の中にはいろんなことが書かれていましたけれども、二つだけ今ここであげれば……。様々な科学の分野がこの一つのプロジェクトのために結集することができた。こんなにすばらしいことはない。こんなに驚くことはない。というのが一点。それからもう一つは、それほど驚くべきことではないかもしれないが、つまり、どちらかというと強調したい順位からいうとトップではないけれども、これだけの大計画が全く秘密のうちに行われたということ。もともと、原子爆弾の誕生は、秘密だったんだね。
■アンソニー・ケイブ・ブラウン (Anthony Cave Brown)の仕事
それでそのことが世の中に解るようになるっていうのは、実は、アメリカの政府が機密文書の公開をするようになったからです。現時点でも機密文書は山ほどありますが、法律によって──30年だったと思いますが──30年経つと公開しなければならない、ということがあるんですね。国家の安全保障に関わるようなこと、これは秘密にしていいんですよ。つまり普通の人は知らない、市民は知らない。とんでもないことだと思いますが、秘密をなくしてしまうと国家そのものが存続できない、というふうに考えて30年間は秘密にしていいという法律が作られている。
さて、アンソニーケイブ・ブラウンという人がいます。イギリス生まれ。今国籍がどうなっているかは僕は知りません。1970年ぐらいまではイギリスの新聞社というか通信社の記者の仕事をしていました。もちろんアメリカだとかカナダとかでも名前は知られていたと思います。この人は、Bodyguard of Liesという、たぶん1974年ぐらいに書いた本があります。Bodyguard of Liesです。Liesというのは嘘だよね。Bodyguardはわかるよね。で、ブラウンはまだ今でも活躍してます。最近は何してるかというと、中東のたとえばサウジアラビアと、アメリカのどっかの資本がくっついて、あそこに生産される石油から生まれる利益をどうやってうまいことモノにするか、というようなことをめぐって「スパイ大作戦」があるということを書いている。アンソニー・ケイブ・ブラウンという人は、スパイを追いかけるのがうまいんですよ。追いかけるといっても事が起こってしばらく経ってから、実はこういうスパイ活動があったということを、いろいろ調べてこれを描き出す、そういうジャーナリスト。で、僕の命名は「スパイ・ジャーナリズム」です。このBodyguard of Liesというのは──「D-Day」ってのを知ってるよね、ノルマンディー上陸作戦。これは、成功したんですが「実はD-Dayの背後には大変なスパイ大戦争があった」ということをケイブ・ブラウンさんが書いた本です。
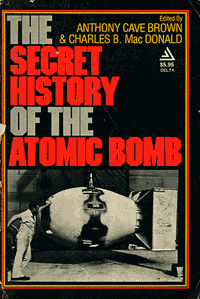 そのケイブ・ブラウンがThe Secret History of the Atomic Bombというのを書いたんですね。1977年です。1945年から30年たった時点でアメリカの公文書で今まで秘密になってたものが全部公開された。それをブラウンさんが集めて編集したものがこれ。ブラウンさんともう一人、チャールズ・マクドナルドという人が編集をしています。チャールズ・マクドナルドさんは、これはやっぱり戦争の歴史──戦記物っていうのかな──そういうのを書くジャーナリスト。二人共ジャーナリストです。さっきから「ジャーナリスト」という言葉を簡単に使っておりますが、そのジャーナリストがいて初めて、こんなことが起っていたのかということを多くの人が知ることができるんです。ところがですね、もうこの本ほとんど手に入らない。という状況です。寺町君であったら、核兵器産業の陰謀であろうと思うかもしれないけど、よくわからないけれどももう手に入らない。
そのケイブ・ブラウンがThe Secret History of the Atomic Bombというのを書いたんですね。1977年です。1945年から30年たった時点でアメリカの公文書で今まで秘密になってたものが全部公開された。それをブラウンさんが集めて編集したものがこれ。ブラウンさんともう一人、チャールズ・マクドナルドという人が編集をしています。チャールズ・マクドナルドさんは、これはやっぱり戦争の歴史──戦記物っていうのかな──そういうのを書くジャーナリスト。二人共ジャーナリストです。さっきから「ジャーナリスト」という言葉を簡単に使っておりますが、そのジャーナリストがいて初めて、こんなことが起っていたのかということを多くの人が知ることができるんです。ところがですね、もうこの本ほとんど手に入らない。という状況です。寺町君であったら、核兵器産業の陰謀であろうと思うかもしれないけど、よくわからないけれどももう手に入らない。
■リチャード・ローズの仕事
アンソニー・ケイブ・ブラウンという人がこういう古い──古いと言っても30年ぐらい前の──文書を集めて作った本を見て、ぼくはビックリしました。ものすごいことが起こっている。というわけですが、みなさんにお配りした資料は、リチャード・ローズという人が書いた本を紹介してますね。で、分量的に言うとこれはもっとすごいんですが、これを書くのにリチャード・ローズは7年ぐらいかかってます。彼の書き方は、いわゆる文献とか、それからドキュメント、文書、とにかくすでにいままで発表されたものを頼りにして、もう一回再構成するんだよね。そういう手法です。分野は何だったかと言うと、ノンフィクションだった。あるいは人々はですね、これを歴史研究だと言います。私はリチャード・ローズのこの本を読んで、一番最初にもちろん彼のですね、前書きというか、言葉が書いてますが、その次の第1章シラードという人の話で始まってますね。そのシラードは、H. G. ウェルズという人の本を読んだって書いてます。H. G. ウェルズの本を読んだってことは、僕は実は知らなかった。で、リチャード・ローズのこの本を読んで初めてそんなことがあったのかなと思って、H. G. ウェルズを最近日本で翻訳されて出版されたので読んだ。そしたらすごいんですよね。というわけで、このH. G. ウェルズの本から一部を抜粋して資料にしました。というわけでその両方を見ておいてください。H. G. ウェルズの方はいわばSFといえばSFだし、小説といえば小説だし、これは歴史ではない。がしかしH. G. ウェルズ自身は、歴史ジャーナリズムみたいな仕事もしています。それからもうひとつはウェルズの頭の中ではこのSFも実は自分の世界認識を書いたものだということにまちがいないと思います。というわけで、ひょっとしたらみなさんが考えているジャーナリズムの境界線を破ってしまって、ジャーナリズムなんてのはそんなはっきり輪郭が見えないんじゃないかという不安におちいっているかもしれませんが、これも読んでおいといてください。時間がないので今日はここまでにします。
授業日: 2002年5月28日; テープ担当学生:小西潤、小堀薫、小南真利、山藤石州